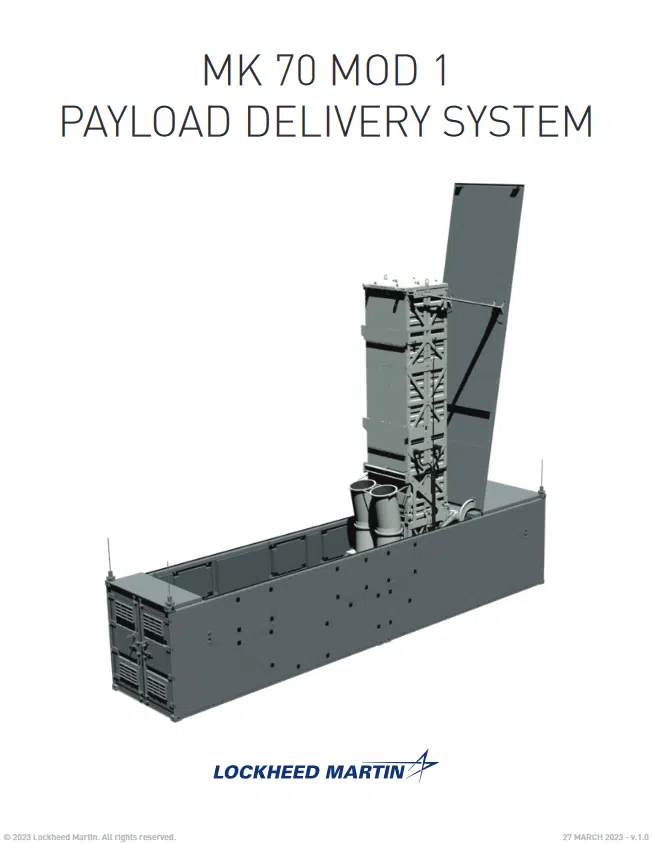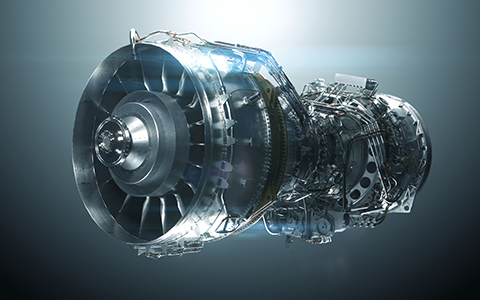ペナントに書かれた1984年
赤い屋根の小さな家の前に立っていた。
庭には主の持ち物が乱雑に積まれている。カーテンは取り外され、家の中には畳の上に布団だけが残されていた。
庭に戻ると、デザインされたタイル類がはがされて箱詰めされており、隣にはお土産用のペナントがたくさん置いてある。
ペナントは三角形のタオルに観光地の色々なデザインがされており、昭和の定番お土産だった。ペナントレースのペナントもこれが語源となっている。
今は亡き主は、かつて庭いじりや旅行が趣味だったのだろうか。これらは人目に付かないように、床下に隠されていたようだ。遺品整理の際に見つけられ、持ち出されたのだ。
その中の一枚のペナントを手に取ると、端に1984年と書かれていた。
『1984年』
その時、目の前に赤いランドセルの女の子が通りがかり、隣の女の子に笑顔で話しかける。
『〇〇ちゃん、虐められて死んだって』
読んだことすら忘れていた、イギリスの作家ジョージ・オーウェルのディストピアSF小説『1984年』
独裁政権に思想監視され、国民は階層別に分けられ、仮想敵国への憎しみを愛国心へと変える事を強要されている。
今、日本において政治的な独裁政権はないが、SNSでの独裁、思想統制が進んでいる。子供達のSNSグループでは、既読が少しでも遅いと非難されるという。それが原因で不登校になる子もいる。
実体のない仮想空間での情報のやり取りが、現実社会の行動にも大きな影響を与えている世界。
自分は既にこの『1984年』に描かれた世界に居るのではないだろうか。